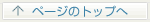死亡による逸失利益の解説
このページでは、交通事故で死亡された方の遺族が賠償を受けられる可能性のある損害のうち、死亡によって生じうる逸失利益を中心とした問題につき、ポイントを絞って解説しています。
死亡による「逸失利益」の概要
死亡による逸失利益とは何か
事故によって被害者が死亡したことによって、将来にわたって、事故がなければ得られていた収入を失うことがあります。
死亡による逸失利益は、この「事故があったために、本来得られるはずだったのに得られなくなった収入」をいい、この逸失利益も賠償の対象となります。
死亡逸失利益の具体的イメージ
死亡逸失利益の算定は、若干複雑な計算式を使うのですが、まずはイメージを持っていただくため、具体的な例を見てみたいと思います。
就労者の場合
就労者の場合、基礎収入から、本人の生活費割合を控除し、就労可能年数に対応する係数(ライプニッツ係数)を乗じて算定します。
(例)
(被害者の状況)
死亡時、年齢40歳、年収600万円、一家の支柱だった場合
生活費控除割合 30~40%
(計算式)
稼動年数は、27年(40歳から67歳まで)
600万円(事故前の収入) × 60%~70%(生活費割合を控除したもの)
× 14.643(27年の場合の中間利息を控除するための係数)
= 5271万4800円~6150万0600円
18歳未満の未就労者の場合
この場合には、男女別平均給与額(年収)から、本人の生活費割合を控除し、稼動年数に応じた係数(中間利息を控除するためのライプニッツ係数という係数)を乗じて算定することが一般的です。
死亡による逸失利益の算定方法
死亡による逸失利益については、以下のような計算式で算出します。
(年間基礎収入額(*1)-年間生活費を控除(*2))
× 死亡時の「就労可能年数」(*3)に対応する「ライプニッツ係数」(*4)
*1 「基礎収入」とは
基礎収入とは、逸失利益を算定するための基礎とすべき収入金額のことをいいます。
*2 「生活費控除」とは
基礎収入から、生活費相当分を控除します。それは、「逸失利益」とは、生存していれば得られたであろう収入であるところ、同様に生存していればかかるはずだった「生活費」がいらなくなることから、その分を控除することが公平と考えられるからです。
生活費控除は、具体的な金額ではなく、概ね以下のような料率で控除されることが実務上多く見られます。
● 一家の支柱
被扶養者1人の場合・・・・・40%
被扶養者2人以上の場合・・・30%
● 女性(主婦、独身を含む)・・・30%
(女子年少者は40~45%)
● 男性(独身、幼児を含む)・・・・50%
なお、年金収入の場合、裁判実務では、生活費控除率を原則的な基準より高くする例(60%程度)も少なくありません。
*3 「就労可能年数」とは
「逸失利益」(生存していれば得られたであろう収入)の算出の要素として、「就労可能年数」(就労できたであろう年数)を算定します。
現在の実務では、就労の終期は67歳として扱うのが一般的です。
例えば、45歳で亡くなった被害者の就労可能年数は、22年(67歳-45歳) となるのが原則です。
ただし、事故時67歳を超える被害者でも、就労の可能性が高ければ、逸失利益を認めるのが実務の方向です。またこの場合の就労可能年数は、事故時の年齢における平均余命年数の約2分の1を就労可能年数とする扱いが多く見られます。
*4 「ライプニッツ係数」とは
これは、「中間利息」を控除するための係数です。
「逸失利益」とは、生存していれば得られたであろう収入です。ということは、本来、事故の翌年の逸失利益は翌年に得られるはずですが、事故から30年後の逸失利益は、本来30年後にしか得られません。
しかしながら、交通事故の賠償では、事故直後から就労可能年数の終期までの数十年間分の逸失利益を、前もって一括払いがなされます。そうすると、数年後、十数年後、数十年後に得られるはずの逸失利益を前もって得られることによって被害者には利息相当分の利益が生じることになります。
それで、衡平の観念から、こうした利息分の利益を控除する必要があり、そのために使用される係数が「ライプニッツ係数」というものです。年数とライプニッツ係数の対応は以下の表のとおりです。
| 期間(年) | ライプニッツ係数 | 期間(年) | ライプニッツ係数 |
|---|---|---|---|
| 1年 | 0.952 | 35年 | 16.374 |
| 2年 | 1.859 | 36年 | 16.547 |
| 3年 | 2.723 | 37年 | 16.711 |
| 4年 | 3.546 | 38年 | 16.868 |
| 5年 | 4.329 | 39年 | 17.017 |
| 6年 | 5.076 | 40年 | 17.159 |
| 7年 | 5.786 | 41年 | 17.294 |
| 8年 | 6.463 | 42年 | 17.423 |
| 9年 | 7.108 | 43年 | 17.546 |
| 10年 | 7.722 | 44年 | 17.663 |
| 11年 | 8.306 | 45年 | 17.774 |
| 12年 | 8.863 | 46年 | 17.880 |
| 13年 | 9.394 | 47年 | 17.981 |
| 14年 | 9.899 | 48年 | 18.077 |
| 15年 | 10.380 | 49年 | 18.169 |
| 16年 | 10.838 | 50年 | 18.256 |
| 17年 | 11.274 | 51年 | 18.339 |
| 18年 | 11.690 | 52年 | 18.418 |
| 19年 | 12.085 | 53年 | 18.493 |
| 20年 | 12.462 | 54年 | 18.565 |
| 21年 | 12.821 | 55年 | 18.633 |
| 22年 | 13.163 | 56年 | 18.699 |
| 23年 | 13.489 | 57年 | 18.761 |
| 24年 | 13.799 | 58年 | 18.820 |
| 25年 | 14.094 | 59年 | 18.876 |
| 26年 | 14.375 | 60年 | 18.929 |
| 27年 | 14.643 | 61年 | 18.980 |
| 28年 | 14.898 | 62年 | 19.029 |
| 29年 | 15.141 | 63年 | 19.075 |
| 30年 | 15.372 | 64年 | 19.119 |
| 31年 | 15.593 | 65年 | 19.161 |
| 32年 | 15.803 | 66年 | 19.201 |
| 33年 | 16.003 | 67年 | 19.239 |
| 34年 | 16.193 |
基礎収入に関する諸問題
死亡による逸失利益を算定する基礎となるのは、被害者本人の基礎収入です。これについて、実務上問題となりうる点を中心に、被害者本人の職業・立場に応じた考え方をご説明します。
給与所得者
基礎収入の考え方
民間の会社員(従業員)や公務員などの給与所得者であれば、源泉徴収票で1年間の年収が判明しますので、これを基礎収入とすることが実務上最も多く取られています。
将来の昇給は考慮されるか
給与所得者の基礎収入の算定にあたり、将来の昇給は考慮されるのでしょうか。
この点は基本的には困難です。しかし、最高裁昭和43年8月27日判決は、将来、昇給等による所得の増加があったであろうことが、証拠に基づき相当の確かさをもって推定できる場合には、予測できる範囲内で昇給等の回数や金額等を控えめに見積もって基礎収入とすることができる旨判示しました。
それで、上のような観点から、「相当の確かさ」という程度に立証ができる場合、将来の昇給を主張できるかもしれません。例えば、公務員や大企業など、労働者の昇給基準が明確に定められ、これがある程度在籍年数によるものである場合などがその例といえます。
若年者の場合の基礎収入
また、若年者の場合、一般的に事故に遭った時点での収入が低額であることが少なくありません。この場合、将来、生涯を通じて賃金センサスの学歴計・全年齢の平均賃金を得られる蓋然性がある場合には、死亡時の現実の賃金ではなく、賃金センサスの「学歴計・全年齢」の平均賃金を基礎収入とするという扱いが実務上なされています。
幼児・児童・生徒・学生
基礎収入の考え方
幼児・児童・生徒・学生等の場合、どのように基礎収入を算定するのでしょうか。
この場合、実務上、基礎収入は、いわゆる賃金センサスの第1巻第1表の「産業計・企業規模計・学歴計・男女別全年齢平均」の賃金額によることが多いといえます。
しかし、大学生の場合には、全学歴計の賃金センサスではなく、大卒の賃金センサスを利用して基礎収入額を算定することが一般的といえます。
また、高校生であっても、本人が大学進学を希望しており、大学進学の可能性が一定程度あれば、大卒の賃金センサスを基準に算定することがあります。
就労開始時期
なお、幼児・児童・生徒などの場合、逸失利益の算定実務では、18歳から働くものと仮定して計算をします。それは、死亡直後から平均賃金の収入があったものとして計算することは現実的ではないからです。
他方、大学生の場合には、大学卒業時から働くものと仮定して計算をします。
家事従事者の場合
被害者本人が家事従事者(主婦)である場合、どのように基礎収入を算定するのでしょうか。
この場合、実務上、基礎収入は、いわゆる賃金センサスの女子労働者の平均賃金額によることが多いといえます。ただし、それ以上の収入があるときは現実の収入額を基礎とします。なお、現実収入と家事労働分の合算は、一般的には認められていません。
事業所得者の場合
事業所得者については、原則として、交通事故で死亡する前年の確定申告所得を基礎収入とします。ただし、事業所得にそれなりの変動がある場合、事故前数年分の申告所得に基づき算定することもあります。
会社役員の場合
原則
会社役員の報酬については、労働者の賃金とは別の考慮が必要です。役員報酬には、労務提供の対価部分と実質的に会社の利益配当である部分があるとされており、前者については逸失利益算定のための基礎収入となりますが、後者は否定されます。
それで、実務上争いとなることが多いのは、役員報酬のうち、どの程度の割合が労務提供の対価部分であるか否かです。これについては、会社の規模、役員の地位、役員の具体的な職務内容、稼働状況、役員報酬額、会社の利益状況など、諸般の事情を考慮して判断されます。
考慮要素
具体的な考慮要素については以下のようなものがあります。
■ 会社の規模
例えば規模の大きな企業であり、かついわゆる「雇われ」の役員である場合、役員報酬の全額に近い部分が労務提供の対価部分と判断されることが多いと考えられます。
他方、小規模なオーナー会社であり、当該役員が会社のオーナーであるという場合には、職務内容に対して役員報酬が高額であると評価され、役員報酬のうちに利益配当的部分が占める割合が相対的に多く評価されることがあります。
■ 役員の地位・職務内容・稼働状況
その役員が名目的な役員であって、現実に役員としての職務を行っていないにもかかわらず役員報酬を受領しているという場合、労務対価部分がないとされ、役員報酬が基礎収入として算入されないことが一般的です。例えば、オーナー社長の近親者が登記上名目的に役員になっている、という場合などです。
また、職務内容に関していえば、例えば、小規模会社であって役員が営業や管理業務をほぼ一人で切り盛りし、他の労働者と同様にフルに実働しているという場合、労務対価部分が高い割合となります。
他方、同じ社内において、役員でないサラリーマンと比較し、年齢が近く仕事内容に大差がないのに支給額が大きく異なるといった事情がある場合、利益配当部分が大きく認められることがあります。
■ 会社の利益状況等
当該役員が死亡した後、会社の売上が大きく下がったり利益が減少したという状況がある場合、当該役員が具体的に稼働・職務遂行していたことの要素として、役員報酬のうち労務対価部分の割合が高く認定されることがあります。
個人事業と同視できる個人会社の場合
個人事業と実質的に同視できるような個人会社の場合、まれにですが、役員報酬相当額に加え会社の営業利益を逸失利益として認定されることがあります。この場合、会社と代表者が実質的に一体であること等の詳細な立証が必要となります。
年金受給者
被害者本人が年金受給者である場合、どのように基礎収入を算定するのでしょうか。
この点、裁判例は、老齢年金,障害年金につき、死亡逸失利益の基礎収入とすることを認めています。
他方、裁判例は、遺族年金、年金恩給である扶助料については、基礎収入として認められないと判断しています。
なお、以上のほか、年金受給者たる被害者本人が家事従事者であった場合、家事労働の逸失利益も認められる場合もあります。
ご注意事項
本ページの内容は、執筆時点で有効な法令・法解釈・基準に基づいており、執筆後の法改正その他の事情の変化に対応していないことがありますので、くれぐれもご注意ください。